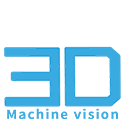ここでは、3Dセンサーの6つの計測方法について、簡単に特徴をご紹介します。「3Dセンサーの選び方が分からない!」という方は、ぜひ参考にして下さい。
3Dセンサとは
3Dセンサは、物体や環境の三次元的な情報を検出する技術で、距離、形状、位置、動きなどのデータを取得し、物体の立体的な特性を認識することができます。光学的、音響的、電磁的な方法を使用し、精度とリアルタイム性に優れており、自動運転車やロボット、仮想現実など、幅広い分野で活用されています。現実世界の物体をデジタル空間に取り込むための重要なセンシング機器です。

- 測定範囲が広く、様々なワークに対応
- コントローラー不要、本体のみで測定可能
- 温度安定性に優れた頑丈な筐体

- 3200point/プロファイルの微細測定が可能
- 従来製品比3倍の面積を持つ大口径受光レンズ
- 全方向位置補正機能を搭載

- 納品日より5年間の製品保証
- ソフトウェアの導入トレーニングが可能
- リモートor出張メンテナンスに対応
「3Dマシンビジョン」と検索して上位表示されるメーカーや販売代理店をピックアップ。その22社の公式HPの情報から「計測手法が最も豊富だったLINX」
「業界ごとの実績が最も豊富だったキーエンス」「唯一24時間のヘルプデスクを提供しているSICK」をそれぞれ選出しています。(情報は2021年11月19日時点)
三角測量法
光切断法
光切断法とは、ライン状のレーザー光を対象物に照射し、その反射光から、対象物断面の高さ・形状・位置をデータとして取得する計測法です。長さや幅、高さ、面積、体積、大きさなどの計測や、正しい部品かどうかの検知をすることが可能です。電子部品、金属部品、樹脂成形品、フィルム・シート、食品・薬品など、さまざまな分野の自動全数検査に活用されています。
ステレオビジョン
2台または3台以上のカメラで対象物の同じ位置を捉え、三角法によりその位置の高さを計測する方法です。人がものを見るときと同じ原理を採用しており、より立体的に物体を認識することが可能です。優れた空間認識が特徴で、リアルタイムで安定した距離測定ができるため、自動運転をアシストする車載カメラとしても用いられています。
縞投影
対象物に縞パターンを照射し、別の方向からCCDカメラ等で撮影して得られた画像を解析する、非接触型の計測手法です。複数の方向からパターン投光することで、死角なく3次元情報を取得することが可能です。また、高精度かつ高速にエリア計測が行えます。ここでは、縞投影法の原理・仕組み、導入のメリットなどを分かりやすくご紹介します。
焦点法
白色干渉法
白色干渉法とは、測定物からの反射光と参照光が重ね合わされたときに発生する干渉縞を利用した測定法です。ナノオーダーでの計測が可能であり、計測精度の基準ともなるような手法です。対象物の材質・色を問わず測定が可能なため、光沢・鏡面状の対象物であっても、安定して測定することができます。ここでは、白色干渉法の原理・仕組み、導入のメリットなどをご紹介します。
共焦点
共焦点法とは、レーザー共焦点光学系(コンフォーカル光学系)を用いた計測法です。反射光が結像する位置にピンホールを置き、レーザーの経路を制限することで、焦点のあった位置のみの光を検出します。光点が小さいため微小な対象物もきちんと捉え、高解像度の三次元画像を得ることが可能です。凹凸やスリーブ、くぼみでの測定にも使用することができます。
合焦点
焦点移動法とも呼ばれ、カメラと対象物の距離を一定量ずつ変動させながら、光学的にフォーカスの合う位置を探索する計測法です。水平方向(XY方向)の計測よりも、Z軸方向の測定が得意で、Z軸方向に取り込める範囲が広い点が特徴です。切削工具や自動車などに使用されるギヤ、ノズル、シールなどの機構部品などの測定に活用されています。
遅延時間法
LiDAR
LiDARは、光束密度の高いレーザー光を光源から照射し、対象物に当たって返ってくるまでの時間を測定することで、対象物までの距離や形状といった情報を計算するシステムです。現在は自動車の自動運転システムなどで活躍している技術であり、半導体や光学レンズなどを組み合わせることで自動検出といった目的でも活用できます。
ToF(Time-of-Flight)
ToF(Time-of-Flight)は、光源から照射された光が、対象物に跳ね返ってくるまでの時間を計測することで距離計測を行う技術です。光速は空気中で秒速30万kmという速度を保っており、光照射から反射光検出までの往復時間をベースにして計算することで、光源から対象物までの距離(片道)を正確に計測することが可能となります。
その他
ラインセンサ
線で撮像するセンサのことで、被写体を垂直方向に移動させ連続で撮影することによって1枚の画像を取得できます。大きな対象物や高精度な分解能が求められるような対象物にラインセンサは適しています。長い対象物であっても1枚の画像で収めることが可能で、あとから画像をつなぐ必要はありません。社会インフラや工場の現場などの検査で活用されています。
エリアセンサ
面で対象物を捉えるセンサのことです。赤外線・超音波・可視光線などのタイプがあり、それぞれのタイプで対象物を捉える仕組みが異なります。ラインセンサよりもリーズナブルで、設定・設置も容易です。ただ大きな対象物は不向き、照明ムラが起こりやすいなどのマイナス点も。自動ドアや作業者の侵入を検知するなどのシーンで活用されています。